はじめに
ニュースやSNSを見ていると、「世界は危機だ」「貧困が深刻だ」「格差が拡大している」といったネガティブな話題ばかりが目に入ります。
でも、本当にそうなのでしょうか?
『ファクトフルネス(FACTFULNESS)』は、そんな“思い込み”に一石を投じる一冊です。
世界を正しく読み解くために必要なのは、「感情」ではなく「データと事実」。
この本を読んで、私は改めて「世界を見る目」をアップデートする大切さを感じました。
- 「実は世界は良くなっている」と知ることで、今の自分を見つめ直すきっかけになる
- 数字を使って考える習慣が、自分を守る武器になる
- 不安や混乱の時代でも、“冷静な希望”を持てるようになる
書籍情報
- 書名:ファクトフルネス(FACTFULNESS)
- 著者:ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド
- 訳者:上杉周作、関美和
- 出版社:日経BP社
- 出版年:2019年(原著2018年)
- ジャンル:教養/データ/社会
- ページ数:400ページ
内容概要:
医師・公衆衛生学者として世界各国で活動したハンス・ロスリングが、「世界は悪くなっている」という誤解に立ち向かう。データをもとに、10の“思い込みの本能”を解きほぐすことで、世界をより正確に理解するための方法を説くベストセラー。
こんな人におすすめ:
- ニュースや世界情勢に漠然とした不安がある人
- 投資やビジネスにおいて“事実ベースの思考”を身につけたい人
- 「世界は悪くなっている」と思っている人
- SNSやメディアの情報をうのみにせず、正しく判断したい人
本書のポイント:10の思い込みの本能
著者は、世界に対する誤解が生まれる原因として、私たちの「思い込みの本能」を指摘します。
たとえば:
- 分断本能:「世界は先進国と途上国に分かれている」
- ネガティブ本能:「世界はどんどん悪くなっている」
- 直線本能:「今の傾向がそのまま続くと考える」
こうした思い込みが、実際のデータと大きくズレた世界観を作り上げてしまうのです。
私の感想(3つの視点から)
1、世界は良い方向に向かっている
アジアやアフリカなどの国だけではなく、自分自身も感じる感覚的にも本当にそうだと思います。当たり前ですが、「日本も豊かになっている」。自分の昔のことと比べれば
- クーラーは当たり前にある
- 外食は気軽にできる
- 海外旅行だって珍しいものではなくなった
「失われた30年」と言われている日本でも、30年前には考えられなかったような暮らしが、今は当たり前になっているんです。
この本は、“世界のこと”を語っているようで、実は“自分自身の今”にも気づきを与えてくれます。
2、数字で語り、数字を疑う
兎にも角にも「データで語ること」。でも同時に、「その数字の裏を読むこと」も重要だと感じさせられました。
- 数字を見るだけではなく、比較軸を持つこと
- 現状のまま推移するという“直線本能”を疑うこと
- ゆっくりとした変化を見落とさないこと
「数字は嘘をつかない」が、「数字の見せ方」は嘘をつくことがある——。
この意識を持つことで、日々のニュースや経済指標への見方もぐっと変わると思いました。
3、決めつけないこと
今も“先進国 vs 発展途上国”という二分構造で語られることが多いですが、実際には中間層が急増し、ライフスタイルも多様化しています。
「発展途上国の当たり前は、自分たちの当たり前にならない」
そんな思い込みも、時間と共に崩れていくことがあります。
思い返せば、私たち自身の生活も激変しました。
最近で言えば、コロナ禍によるオンライン化。
数年前までは想像もつかなかったような働き方や学び方が、いまや常識になっています。
未来を語るとき、“過去の延長線上だけ”で考えるのは危険です。
この本を通じて、「常に価値観をアップデートする」姿勢の重要性を再認識しました。
まとめ
『ファクトフルネス』は、世界をバラ色に描いた楽観主義の本ではありません。
むしろ「現実を正しく見ることで、適切な行動ができる」と教えてくれる、冷静で、でも前向きな“現実主義の書”です。
事実を知ることで、不安が和らぎ、世界が少しだけ優しく見えるようになる。そんな読後感を味わいたい方には、ぜひおすすめしたい一冊です。
 Rock
Rock自身の知識アップデートを怠らず、常に様々な視点でデータを読み解き、「謙虚さ」と「好奇心」を持つことが大切だと思いました!
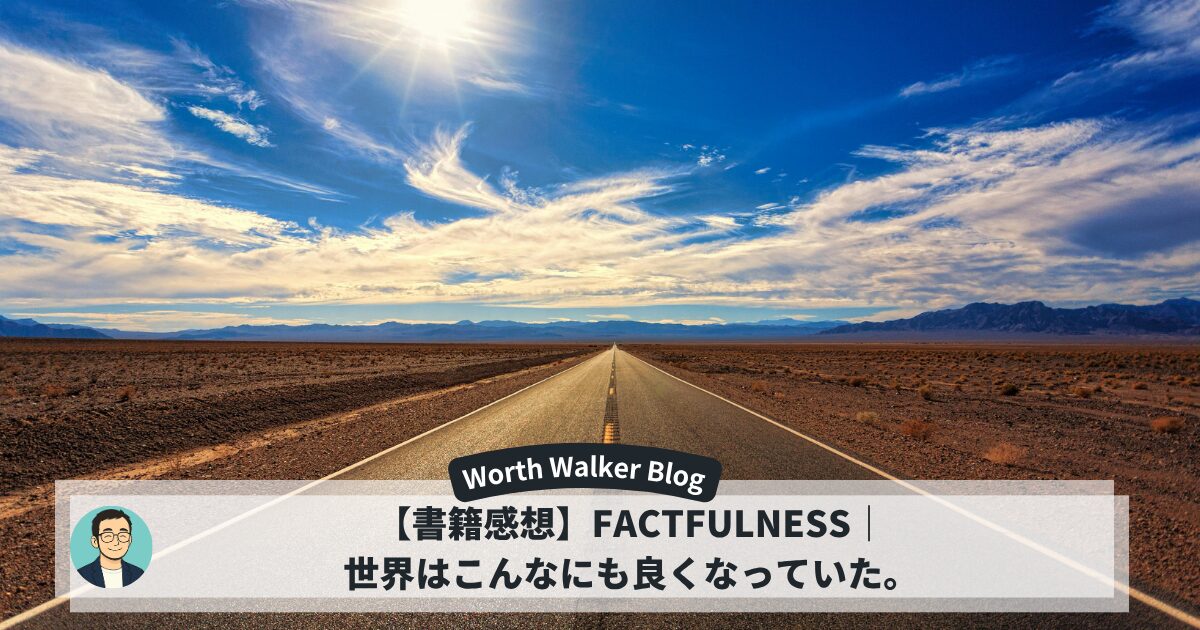
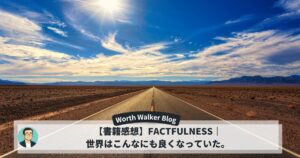

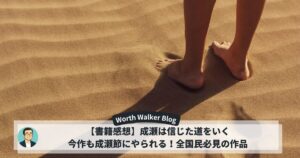

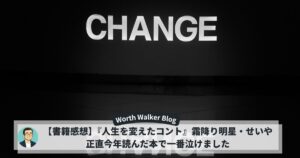
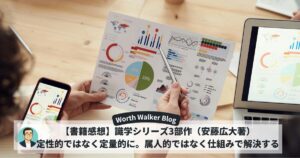
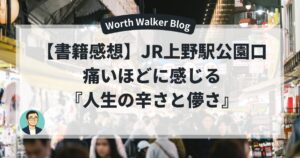
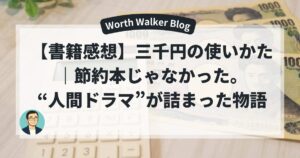


コメント