はじめに
「節約術の本だと思って読んだら、圧倒的な人間ドラマを見せつけられた」読書後、そんな感想を持ちました。
それが「原田ひ香」さんの『三千円の使いかた』です。
タイトルから“お金のノウハウ”術を学べる本なのかな?と思われるかもですが、それ以上に「お金をどう使うか」ということ、「人生をどう生きるか」ということを考えさせられる素晴らしい作品でした。
- タイトルからは想像できない「人間ドラマ」の深さ
- お金をどう使うか=どう生きるかを描いた作品
- 心を揺さぶられた言葉たちを引用でご紹介
書籍情報
- 書名: 三千円の使いかた
- 著者: 原田 ひ香(小説家)
- 出版社: 中央公論新社(中公文庫)
- 出版年: 2018年
- ジャンル: 人生小説・お金と暮らし
- ページ数: 300ページ
内容概要:
「節約のハウツー本」かと思いきや、じつは家族三世代を描いた心温まる人間ドラマ。
“お金の使いかた”を軸に、仕事、老後、恋愛、家族、孤独など、誰もが抱える人生のテーマをやさしく照らしてくれる。人生を豊かにするための「お金とのつきあい方」に、そっと気づきを与えてくれる一冊です。
こんな人におすすめ:
- 節約やお金の話を、人生全体の視点から捉え直したい人
- 就職・結婚・子育て・老後など、ライフステージの変化に向き合っている人
- 小説としても楽しみながら「生き方のヒント」が欲しい人
タイトルに騙された?思っている程、節約術の本ではない!?
人は三千円の使い方で人生が決まるよ
~中略~三千円くらいの少額のお金で買うもの、選ぶもの、三千円ですることが結局、人生を形作っていく
引用:『三千円の使いかた』原田 ひ香
タイトルがタイトルなので、お金に対する価値観が変わったりするのかなと思いましたが、究極言うと、上記の引用部分がお金の使いかたの話、節約の全て。
お金をどう使うか?という具体的なやり方の話というよりも、個性豊かな主人公一家である御厨家のストーリーを通して、それぞれの年代、立場、状況を通して、お金との付き合い方、生き方について考えさせられる内容でした。
只々、圧倒的な人間ドラマ!
むしろこの人間ドラマが面白い!
主人公一家である御厨家(と繋がる人々)を、それぞれの主眼をもとに物語が展開していく。各世代で感じている悩みや葛藤、同世代でなくても共感できるリアルさに、一気に物語に引き込まれる。
しかも同年代の悩みの共感だけでなく、これからきっと考える必要があるんだろうなという将来の話、生きる上での漠然とした不安など、読み進めていく中で、様々な登場人物に感情移入して、物凄く考えさせられました。
心を揺さぶられた言葉たち
智子から五千円をもらったことは、琴子に大きな変化をもたらした。嬉しかった。単純に、嬉しかった。まだ、自分もお金を稼ぐことができるのか
引用:『三千円の使いかた』原田 ひ香
御厨家の祖母である「琴子」が、息子の嫁である「智子」から、ひょんなことからおせち料理の教室の手伝いを依頼され、その御礼に謝礼を渡されたシーン。
琴子がお金に対する悩みがあった中、自分の今までの経験を活かし、料理を教えるということで、色んな人に感謝され、その感情が揺れ動く様を物凄く感じました。
だけど、久しぶりに自分を必要だと思ってくれる人がいた。それはあの時、ハンカチを買いに来た夫に、「僕と交際してください」と言われた時以来だった気がして、なんだか少し目頭が熱くなった
引用:『三千円の使いかた』原田 ひ香
人に感謝されたいということ、お金を得たいということ、琴子が今後の老後を考える時に、心から思ったこと。
70過ぎの年齢を気にしつつも、意を決してコンビニのバイトに面接を受けに行ったが、年齢が原因で不採用になってしまう。ただ、コンビニの店長がそんな琴子のことを覚えており、湊屋(有名な和菓子店)のアルバイトの面接を受けないか?と言われた時の話。
夫に交際を申し込まれた時と同様、人に必要とされていると心底思い、琴子自身が誰かに必要とされることに喜びを感じる。そんな情景がまざまざと浮かぶ、心が熱くなりました。
まさに「マズローの欲求段階説」である「承認欲求」を感じました。
人はただ息をして生きるのではなく、人に認められ、人に必要とされ生きる。それが人間の本来の欲求であると思います。
「人生は理不尽なもの。でも、理不尽なことがなかったら、なんのための節約なの?経済なの?節約って、生きていることを受け入れた上ですることよ。費用対効果なんてない、ってことを受け入れてからの節約なのよ。じゃなかったら、私みたいな年寄りはもう死んだ方がいいってことよね」
引用:『三千円の使いかた』原田 ひ香
琴子が知り合った、アルバイトをしながら世界中を放浪している男「小森安生」に言い放った言葉。
安生は、費用対効果を重視、子育てに費用対効果なんてないと言い切る。そんな安生に琴子は、生きていく上での費用対効果なんてない。順番を逆にしてはいけないと怒りながら諭すシーン。
人はなんでもロジックで語れる訳はなく、時に非合理で、費用対効果なんて考えなくても、只々理不尽な中でも生きていくしかない。けど、それが人間らしさではないかと気付かされたシーン。
まとめ
一生懸命生きること、丁寧に生きること、一言で言うとそういうことに繋がるんだろうが、様々な人間模様を見て感じたことは、全員が様々な事象を通して、その他の人と真剣に向き合い、しっかりと対話して、お互いを理解しようと努めたから、未来が拓けたということ。
時にそこには喧嘩もあるが、それでもお互いの気持ちをはっきりと相手に伝えること、そうすることで初めて物語は動き出す。
- 琴子(祖母)が、おせち教室でお金を手にした時、人から感謝されたい、お金を得たいと、気付いただけでなく、アルバイトの面接に行ったから、和菓子店の話がきた
- 美帆(次女)が、保護犬と出会い犬を飼いたいと思い節約に目覚め、セミナーに行ったから翔平と出会った。そして、翔平がちゃんと自身の状況を話して、美帆も本音を伝え、家族を巻き込んだから最後のハッピーエンドがあった
 Rock
Rock人生を真剣に生きること。しっかりと地に足をつけ行動すること。だから人生が切り開かれる。そういうことを感じました。
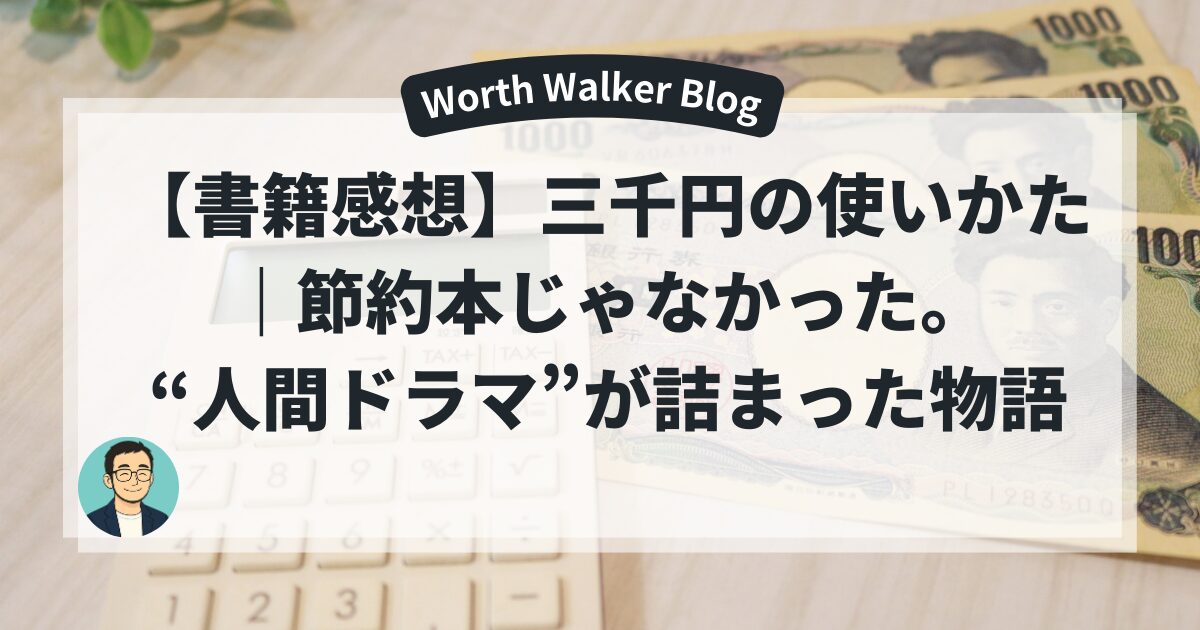
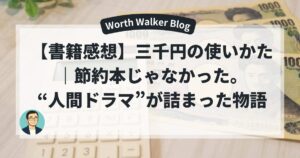

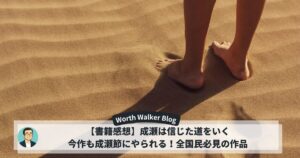

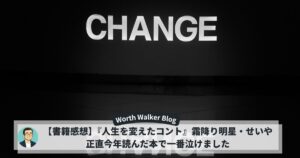
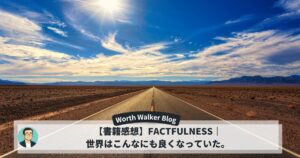
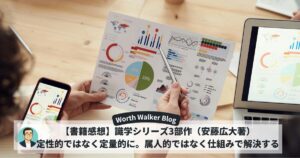
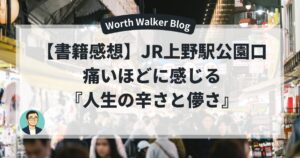


コメント